 学級通信 足柄高等学校 2年2組 2002年
学級通信 足柄高等学校 2年2組 2002年
| 学級通信 | 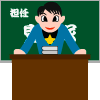 昨年度に続いて、学級通信 SPINNING WHEEL 2001を発行しました。 昨年度に続いて、学級通信 SPINNING WHEEL 2001を発行しました。学級は2年2組で理系の生徒たちです。理系は数学を週に6時間、物理を3時間、化学を4時間学習します。3年生になると、理科一科目を選択させて、徹底的に磨き上げようというカリキュラムです。 【3年生を担任することなく、西湘高校へ異動してしまったのが残念】 |
|
| 2002年 7月9日 |
第1号 | 進路説明会 6月28日 池田博明 期末試験も真近い6月28日(木)のLHRを利用して進路説明会が開催された。進路指導部の石塚先生のお話に続いて、教育実習生で来校した本校の卒業生四名の体験談が話された。 体験談はそれぞれ個性ある内容だったが、私がいちばん驚いたのは全員が運動部で活動していたということであった。部活動と勉強の両立は容易ではない。浪人して進学したひともいた。それにしても、目的を持って勉強することの重要さは感じられたのではないだろうか。私も中学・高校時代と運動部だったので感慨深かった。 三者面談あるいは二者面談で家庭学習時間が一時間以下という人もいるが、それでは大学には合格しない。だいいち、大学は学問をするところである。 どんなに部活動がつらくても、やりたい勉強があって、時間が足りないという気持ちが無ければ、大学に進学する意味はない。 高校1年・2年時代の私は家庭で毎日4時間は勉強していたと思うが、両親は仕事の関係で別居して不在だったので、親に勉強しろと言われたことは一度もない。好きな科目があったので、その勉強をするのは楽しかった。 さすがに部活動が終了した高校3年の10月以降は寝る時間を惜しんで、受験のための勉強(五教科七科目)もしたが、当時の日記には「受験のための勉強はつらい。早く好きな科目だけの勉強がしたい」などと弱音が書き記されている。後になってしまうと、こういった事は忘れてしまうものだが、中学の頃から毎日、日記を書いていたので、その類の泣き言が毎日のように記録されているのだった。自分の経験からしても、当時の勉強の日々は、つらかったと言える。 さらに追い討ちをかけるような言葉もあった。 運動部の顧問の先生は私たちによくこう言っていた。「君たちは部活動をやっていない生徒よりも、土壇場で頑張るだけの力を持っているんだ。つまり、やれば必ずできるのだ」と。先輩も繰り返しそう言っていた。ところが、ある日3年の学級担任のS先生が朝のSHRでボソっとつぶやいたのである。 「あのな、やればできるなんていうのはウソだよ。やるかやらないかも能力のうちなんだよ」と。 もちろん、この言葉は私に向けて言われた言葉ではなかった。しかし、瞬間的に私はこの言葉は真実であると感じた。相当なショックであった。その日は一日じゅう動揺しっぱなしであった。 その日をきっかけに、私は「やればできる」という逃げ口上は止めた。やれるだけのことをやろうと決意したのだった。2年生のときにこんな言葉を聞いていたら、もう少しスタートを早く切れたかもしれないが、もう遅かった。 いずれにせよ、勉強は楽ではないのである。 陰山英男『本当の学力をつける本』(文藝春秋) 池田博明 兵庫県の田舎に小さな小学校がある。進学塾もない、山間の公立小学校の卒業生が全国の平均より高い学力を身に付けているという実績で注目された。その実践記録の本である。ここで教育されているのは小学生だが、高校生にも当てはまると思われる耳の痛い指摘がたくさんある。その見出しだけを挙げておく。 学校でできること 読み書き計算の徹底は一生の財産になる 音読は記憶力を高める 低学力は本人の思い込みによる 単位をつけさせることで理解が飛躍する 理解よりもまず練習 家庭でできること まず朝食をきちんととる テレビを一日二時間以上見る子に高学力の子はいない 正しい姿勢を保つ 朝は六時に起きる 朝食はパンよりもご飯の方が頭のためにはいい 学校の授業に集中させる 読書の習慣をつけさせる 学習した内容を子供に説明させてみる などなど。 夏目漱石英訳「HOJIO-KI」と『山月記』の音読 池田博明 国語の期末試験に鴨長明『方丈記』と中島敦『山月記』が出題されていたので、思い出したことがある。ひとつは『方丈記』を英訳したものが夏目漱石全集のなかにあることだ。漱石の英訳は見事なものであり、英文学者・夏目金之介の実力を示している。明治時代の英文学者には途方もない英語力があったと考えてよい。漱石が『文学概論』で論じている英国の詩人やデフォー(『ロビンソン・クルーソー』の作者)、スウィフト(『ガリヴァー旅行記』の作者)といった英文学者の原文に付した和訳も見事なものである。もとの英文とほぼ同じ長さで訳されているのだ。 夏目漱石以外にも新渡戸稲造の『BUSHIDO(武士道)』や岡倉天心の『BOOK OF TEA(茶の本)』、鈴木大拙の『ZEN AND JAPANESE CULTURE(禅と日本文化)』など、最初から英語で書かれたこれらの著作の傑出した出来を見ると、現代の私たちの英語と日本語の語学力のひ弱さを感じてしまう。 明治時代の知識人は幼少の頃は漢文を素読しており、漢語にも強かった。書き言葉と話し言葉が接近してきてさまざまな衝突をしている時代でもあった。そこへ、国際人として活躍する人々の必須の教養として英語も輸入されてきたのである。現代とはまったく異なる言葉の海のまっただ中へ泳ぎだしていった明治人の気概を、これらの著作はじゅうぶんに感じさせてくれる。 ところで、中島敦の『山月記』は見事な和漢混交文で書かれている。簡潔な文体で、音読に滴した文章である。声を出して読んでみるとその素晴らしさはいっそう際(きわ)立つ。 最近、音読の重要性が強調されている。明治大学の齋藤孝『声に出して読みたい日本語』(草思社)がベストセラーになり、いまや同工異曲の本が書店の棚に山積みされている。しかし、ベストセラーとはいえ、齋藤の仕事は一朝一夕になったものではなかった。齋藤は教育学者で、以前から身体感覚を取り戻すという試みを続けていたのである。 齋藤が強調したのは日本人の伝統的な姿勢であった。剣道で剣を構えるときの姿勢のような、下腹に力を入れて一気に気合を入れることが可能な姿勢である。子供にそのような身体感覚を取り戻させることが新たな教育の核心となるという実践研究をずっと行ってきたのである(NHKブックス『身体感覚を取り戻す』2000年)。 音読はそのような身体感覚の蘇生のひとつであった。齋藤の本は他の著者の本とは異なっている。ただ音読に適した文章が選択されているのではない。姿勢や気合といった身体感覚を取り戻すに良い内容の文章が選ばれている。弁天小僧の「知らざァ言って聞かせやしょう」と始まる口上も、歌舞伎役者が「大見栄を切る」動作と合わせて読まれるべきだし、ガマの油売りの口上も油売りの所作事と一緒に理解されるような工夫が隠されているのである。 そして、声を出すには呼吸法が大切である。良い呼吸は口先だけで、できるものではない。腹を使って呼吸する必要がある。また、声を出す前に息を十分に吸わなければならない。息をよく吸うためには貯めておいた息を吐ききることも大切である。息を吐いて、そして息を吸う。この深い繰り返しが、人の力を作るのである。 呼吸の重要性を幸田露伴のような職人気質を理解していた明示の文学者はよく知っていた。露伴は娘の幸田文(あや)に、気合いと呼吸の大切さを鉈(なた)で木を切ることで教えようとする。齋藤のもうひとつの本『理想の国語教科書』(文藝春秋)で、もっとも重要な一篇がこの幸田文の文章である。 齋藤孝は、小学生に紙の名刺で割り箸を折ることができるかどうかという課題を与えて、息と姿勢の大切さを、身体感覚を通して教えてきた。姿勢ができあがっていないと折れないのである。高校生にも同じことが言えるのだ。 ひとと話をするときにあなたは背筋を伸ばしているだろうか。廊下に座って、背中を丸めて話している姿勢は、決して美しくない。立っているときの姿勢が美しいと見えるような文化が、以前の日本には伝統的にあったのではないか。 そう言えば、思い出したことがある。私の所属していた運動部では中学校時代から、常にかかとを上げているように指導されていた。いつも爪先立ちしていなさいというのである。これは腱や筋肉をきたえるためだと教えられていた。中学のときにはかかとを上げていないと、頬に先輩の平手打ちが飛んだ。ジャンプ力が必要な競技なので、納得のいく訓練法だった。 ところで、爪先立ちしてみると分かるが、同時に背中もまっすぐになるのである。立っているときに自然に背筋が伸びることになる。姿勢に対する思わぬ効用があったので、部の伝統になっていたのかもしれない。 |
| 2002年 7月9日 |
第1号4頁目 | Hojio-ki Translation by Soseki Natume Incessant is the change of water where the stream glides or calmly: the spray appears over a cataract, yet vanishes without a moment's delay. Such is the fate of men in the world and of the houses in which they live. Walls standing side by side, tilings vying with one another in loftiness, these are from generations past the abodes of high and low in a mighty town. But none of them has resisted the destructive work of time. Some stand in ruins; others are replaced by new structures. Their possessors too share the same fate with them. Let the place be the same the people as numerous as before, yet we can scarcely meet one out of every ten, with whom we had long ago a chance of coming across. We see our first light in the morning and return to our long home next evening. Our destiny is like bubbles of water. Whence do we come? Whither do we tend? What ails us, what delights us in this unreal world? It is impossible to say. A house with its master, which passes away in a state of perpetual change, may well be compared to a morning-glory with a dew drop upon it. Sometimes the dew falls and the flower remains but only to die in the first sunshine: sometimes the dew survives the drooping flower, yet can not live till the evening. More than forty years of existence have rewarded me with the sight of several wonderful spectacles in this world. On the 28th of April in the 3rd year of Angen(1177) when the wind was raging and the night was boisterous, a fire broke out at eight o'clock in the south-eastern part of the city and spread towards the north-east. The Sujakuden, the Daikyokuden, the Daigakurio and the Mimbusho were all reduced to ashes in one night. (後略) |
| 2002年 9月19日 |
号外 | ナンバー・ワンでなくともオンリー・ワンにはなれる 池田博明 ある本のなかで印象的な言葉を読んだ。上の言葉である。 本は上野吉一『グルメなサル 香水をつけるサル』(2002年,講談社選書)。上野氏は京都大学霊長類研究所の助教授であるが,経歴が変わっている。 岩手県に生まれ,獣医になりたくて北海道大学に進む。しかし,獣医学部に進めず,農学部農芸化学科に進んでそこを卒業した後,大学院は文学研究科(行動科学)へ。霊長類の嗅覚・味覚の研究で博士になった。現在は京都大学で教えている。 「あとがき」によると,上野氏は高校時代に受けた全国模擬試験では偏差値20台だったという。ちなみに,偏差値20は飛びぬけて得点できていなかったということである。3年くらい浪人したようだが,北海道大学に入学できた。そこで当初の目標の獣医学部に進学できなかったのは,「専門課程に進む大学のシステムの問題で」と書いているが,おそらく大学1・2年の教養課程の成績が良くなかったためである。 北海道大学の理系は教養課程の成績の良いもの順に希望の学部に行けるシステムになっていた。成績上位の者で学部学科の定員がうまってしまった場合には,希望の学部に進めないのである。当時は理系約2000名という大きなくくり方だったので,理学部・薬学部・農学部・工学部・獣医学部のどこにでも行ける可能性があった。学生には医学部と水産学部以外のすべての理科系学部に道が開かれていた。ただし,1・2年の成績がよければの話であった。 学生は1・2年の成績によって,ABCDの四区分に分けられ,Aの生徒から希望が受け付けられた。獣医学部も当時は4年生だった(現在は医学部と同様6年生になっている)ので,理系のクラスから進学できたのであった。 ただし,現在の北大は区分が東大方式になっており,当時とは若干状況は異なっている。 この「オンリーワンになれ」という言葉はノーベル化学賞を昨年受賞した野依良治博士も言っていた。 ひとりひとりが違う人間だから,ひとと比べることはないのである。 思春期はとかく他人のまなざしが気になるものだ。自分が他人からどう思われているかが悩みのたねになる。 誰だって他人からよく思われたい。自分を理解して欲しいと思っている。しかし、自分の性格や特徴を変えることは実はとても難しいことなのだ。 自分を改善するために他人の見方が役に立つことも大いにある。しかし、あまり他人の見方にこだわるとそのうち自分が無くなってしまうのだ。 他人から見ると結構、誰でもそれなりの自分があるものである。そして他人から誤解されたって別に構わないのである。つまり他人には誤解する権利だってあるのだ。 ただし,こんなふうに思えるようになったのは自分でも19歳のときだが。 |
| 2003年 3月31日 |
第2 号 |
明日はない 池田博明 学級通信も第1号を7月に、号外を9月に発行しただけで、ようやく第2号を今年度の終わり、2003年3月31日に出そうとしている。もともと生徒の文章を紹介するとともに、私の考えを付属して発行しようという目的の通信であるから、今年は別に修学旅行の文集や写真集も作成されたし、日々の記録としてはデジタル文集も出来上がったので、通信に代わるものはあったと言えるかもしれない。ちなみに、3学年の日々は卒業アルバムに記録される。 さて、思いがけず転勤になってしまったので、私が担任として何かメッセージを伝えられるのは最後になってしまった。あれこれ考えてみたが、学級担任は、けっこういろんな場面でみんなにメッセージを話しているものなので(たとえば「掃除は大事」とか「姿勢をきちんと」などなど)、改めて言うようなこの期にふさわしい言葉はまるで思いつかない。 そこで、私の人生観をくり返しておく。それは、私は、「明日はない」と思っているということである。大学4年のときにウィルス性の急性肝炎で死にそうな目に会って以来、私は毎日、明日の死を覚悟しているということである。「上を向いて歩こう」という歌で有名な坂本九には、「明日がある」という歌がある。「明日があるさ、明日がある。若い僕らには夢がある」という歌詞である。まことにその通りという言葉である。 しかし、実は、私には明日はないんだ。毎日、死を覚悟するなんて、暗い人生だよ、と大抵の人は感じると思う。ところが、そうではないところが不思議である。 病気で死にそうになったとき、私は「末期(まつご)の眼」というものを経験した。死に行くものから見ると、この日常世界はたとえようもなく美しく見えるのであった。ささいな事に感動することもできる。一日一日を大切に過ごすことも可能になる。それまでいい加減だった自分の人生を見直すこともできるし、なにより他人に対してやさしくなれる。やさしくなれるだけでなく、真にきびしくもなれる。みんな明日には死ぬかもしれないんだから。 高校生に伝えることはひとつ。二十歳までのハイ・ティーンの時代に勉強したこと、経験したことで、人間の器(うつわ)が出来あがる。この時期に真剣に勉強に取り組まなかった人は、気の毒だ。本を読むにもいちばん良い時期である。何をしてもあなたの身になる時期である。毎日がダイヤモンドの原石を磨いているようなものである。今日一日しっかり磨けたら、明日は灰になっても(ダイヤモンドはよく燃える。なんと言っても炭素で出来ているのだから)、それなりに立派に光るもの。 デジタル文集には、足柄高校での毎日の天気が記録してある。この文集で一番価値があるのはこの記録だと、私は思っている。学級日誌に記録した何気ない天気欄。5年後、10年後に、あなたが幸いに生きていて、過去をふり返ったとき、いちばんあなたにとって意味がある情報は、戦時下の子供たちとはまったく異なる、そんなささいな、あなたの生きた証しである。 |
| クラス担任 | モットー |  大切にしたいこと:IKEDA=Identity(主体性)、Kindness(思いやり)、 大切にしたいこと:IKEDA=Identity(主体性)、Kindness(思いやり)、Effort(努力)、Decency(品のよさ、親切)、Appreciation(感謝、尊重)。 格言など:Learning by Doing(成すことをもって学ぶ。自分の手や体を動かし、使うことによって学習する。私の中学で全校加盟していたJRC=日本青少年赤十字のモットーでした)、 Sense of Wonder(自然の驚異に感動する心。『沈黙の春』のカーソンの遺著の題名でもある)、 Small Is Beautiful(小さいことは美しいことだ。大量消費の時代の批判)、 Only One Earth(かけがえのない地球。環境保護の心を育てるにはまず教室の掃除から)。 |