BACK TO HOME (=Ikeda Home Library)
◆文字が大きい時は「表示」でフォントを小さく設定して下さい。
森崎東さんの映画を見続けて 池田博明
 私が最初に見た森崎東監督の映画は『喜劇・女は男のふるさとヨ』であった。破天荒な映画であったが、その混沌になにかを感じて以来、森崎さんの映画を見ることがいちばんの楽しみになった。この映画は、松竹で撮っていた新宿芸能社(お座敷ストリップあっせん業)を中心とした『女』シリーズの第一作目だった。次いで、このシリーズ第三作『喜劇・女売り出します』で、主人公・浮子(うわこ)=夏純子と映画の勢いに大感動した。結局この映画を映画館で十回以上見た。 私が最初に見た森崎東監督の映画は『喜劇・女は男のふるさとヨ』であった。破天荒な映画であったが、その混沌になにかを感じて以来、森崎さんの映画を見ることがいちばんの楽しみになった。この映画は、松竹で撮っていた新宿芸能社(お座敷ストリップあっせん業)を中心とした『女』シリーズの第一作目だった。次いで、このシリーズ第三作『喜劇・女売り出します』で、主人公・浮子(うわこ)=夏純子と映画の勢いに大感動した。結局この映画を映画館で十回以上見た。
当時、「キネマ旬報」では“読者の映画評”という企画が始まっていて(当時の編集長は白井佳夫さん)、広島県の平田泰祥君が森崎映画について長編論文(キネ旬ニューウエーブ)を書いていた。1970年頃の森崎さんの映画については平田君の論文が過不足なく、森崎映画の魅力を論じているので、私には付け足すことはない。森崎さんの映画が興行的にもまずまずで、批評もわりと好意的だったのは、なんとこの『喜劇・女売り出します』まで、であった。
その後の森崎映画のほとんどが興行的に失敗し、批評家からも叩かれた。松竹の『女』シリーズは第四作『女生きてます・盛り場渡り鳥』で終わってしまったし(この映画は、超傑作だったが)、ハナ肇の『為五郎』シリーズも森崎さんが引き受けた第五作『生れかわった為五郎』で最終作になってしまった(この映画も、とんでもない傑作だった)。その後の森崎さんの超傑作はまったく客が入らないのが特徴である。堺正章の最初で最後の主演作『街の灯』、東映で撮った『喜劇・特出しヒモ天国』、松竹富士映画『ロケーション』などがそれである。
これら5本の作品中『ロケーション』と『街の灯』がレンタルビデオになっている(ただし、現在は廃盤)。森崎映画の傑作の奇っ怪度を味わうには、これらの映画でも十分である。ちなみに、立川談志がキネマ旬報で日本映画のベスト3を選んだときに、『喜劇・女売り出します』を挙げていた。
NHKの朝の連続ドラマの映画化『藍より青く』や、黒沢明作品の再映画化『野良犬』、ATGの『黒木太郎の愛と冒険』、木下プロの『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言』などは、ややいびつな佳作である。
夏目雅子が主演した『時代屋の女房』や、野村芳太郎の傑作『白昼堂々』を再映画化した『女咲かせます』、浜ちゃん夫婦に誤解から亀裂が入る『釣りバカ日誌・スペシャル』、三国連太郎と佐藤浩一の親子共演の『美味しんぼ』などはそこそこのお客さんの入りだったようだが、どはずれた傑作というわけではなかった。また、『夢見通りの人々』や『塀の中の懲りない面々』は森崎さんらしいところはあるものの、散漫な出来になってしまっていた。
テレビ作品では『帝銀事件』(テレビ朝日制作)が傑作だった。『蒼き狼』はビデオになっている。
今年1998年の『ラブ・レター』は評判がいいし、興行的にも成功したようで、森崎作品としては異例のことだ。しかし、こわくて、まだ見にいっていない。
私が森崎さんとならんで大好きな映画監督である勝新太郎も、ロバート・アルドリッチも死んでしまった。森崎さんにはまだまだ頑張ってほしい。
森崎東資料集を製作中です。
野原藍『にっぽんの喜劇えいが2 森崎東篇』(1984年、映画書房。絶版)に掲載された全ての資料を、本ページに掲載していきたいと思っています。この本は発行者の野原藍さんが心血を注いで作った本です。映画書房の「にっぽんの喜劇えいが」シリーズは第一巻part1が前田陽一篇、第二巻part2が森崎東篇ですが、その後、映画書房は倒産してしまい。本も入手困難となってしまいました。まさに森崎さんの怪作同様の呪われた映画本でしょうか?!(池田博明記)
キネマ旬報掲載拙評に『喜劇・女は度胸』、『街の灯』、『喜劇・特出しヒモ天国』論があります。
森崎東監督 『街の灯』(1974年)の故郷の歌 池田博明
『街の灯』で、堺正章が風景にかぶせて、「故郷の廃家」を歌う。歌詞の大意は「自然は変わらないのに、昔の家は朽ちてしまった」というもので、有明海に向っている五人組にはふさわしい。この歌は、『男はつらいよ・奮闘篇』でも榊原ルミがふるさとへの思いをこめて歌っていた。このときの榊原ルミの役名が花子で、『街の灯』の記憶喪失中の栗田ひろみの名と同じである(森崎さんの『生まれかわった為五郎』の緑魔子の名前もたしか花子はシカ子。記憶違いでした。森崎脚本の『吹けば飛ぶよな男だが』の緑魔子が花子)。
ところで、『街の灯』のブラジル帰りのじいさん(笠智衆)は結局、故郷・有明の里に腰を定めない。昔の恋敵・三木のり平の怒りをもっともとして、身を引くかたちである。(このとき、昔の恋人・鈴木光枝は夕食のつもりで出したおかずを皿から重箱に移している。この心づかいがにくい。後で堺正章がジャーに入れたご飯と共に持って行く)。そして、「パルタモス(出発)じゃ」と再びブラジルへ渡ろうとする。その為に旧式の拳銃に一発の弾をこめて近くの信用金庫から金を奪うのである。
そうなのだ。帰るべき故郷なんて実はどこにもないのである。
じいさんのカバンからは、拳銃や軍人手帳や歯ブラシが出てくる。まるで横井さんのパロディ。横井さんは「ただ今、帰ってまいりました」と言った。じいさんは「帰ってもええじゃろか」と昔の恋人・鈴木光枝にたずねる。横井さんは、横井さん自身の幻想の日本帝国へ帰ってきたのである。また、横井さんは陛下の銃を陛下に返そうと抱いてくる。一方、じいさんは、やはり陛下の銃で強盗をする。横井さんも、陛下に銃を返すのではなく、むしろ銃を陛下に向けるべきだったのではないだろうか。
じいさんの再「出発(パルタモス)」は失敗して、強制送還となる。堺正章と栗田ひろみのパルタモスも成らなかった。森崎東は亡郷のうた、亡国のうたを歌っている。そしてまた、亡郷、亡国の意識に支えられた出発のうたも歌いつづけている。
(池田編『続・現代歌情/唄って、いつかのあの歌』から.1974年9月18日発行)
重層的『街の灯』論 池田博明
まぎれもなく森崎さんの映画で、これまでに森崎さんの映画で一度でも「森崎経験」をした人には
嬉しくなってしまう映画である。期待に胸ふくらませて見に行って、最初の数シーンで、
「いける!」とゾクゾクしてくるのはいいものだ。「森崎映画ならなんでも」と暴言している僕だって、昨年の『藍より青く』
『野良犬』になると、作品を見るよりもむしろ森崎さんの奮闘ぶりが目立ってしまい、暗い気持ちにならざるをえなかったのだ。
このまま、頭がどんどん重くなっていって、ぶったおれてしまうんじゃないか、森崎さん!。
しかし、それは取り越し苦労だったようだ。森崎チームはちゃんと生き残っていたのだ。
森崎チームとは、森崎映画のスタッフとキャスト、それにファンである。

『街の灯』は、東京から九州・有明海までの旅が中心になっているが、この旅にあわせて、これまでの森崎映画を追体験することが出来る。それは二重の喜びだ。
出発点・東京で、主人公チョロ松(堺正章)は、兄(財津一郎)の代理でポン引き稼業、いわば性の下請け稼業で、お座敷ストリップあっせん業の「新宿芸能社」とかたちこそ違え、へその緒は一緒。当人たちは仕掛けて為損じなし「愛情仕掛け人」なんて言っているが、これはむしろ森崎さんの心意気とみるべきだろう。ポン引きは、愛情仕掛け人などと格好いいものではない。その証拠に、調子づいたチョロ松が手練手管を披露すると、田中邦衛は恋人をいたぶられたと怒り、おでん屋の二階を破壊してしまう。これは、『喜劇・女生きてます』の橋本功や『盛り場渡り鳥』の山崎努が家を壊すシーンにつながる。とつ弁ながら真剣に愛情をそそぐ男たち。
壊されたおでん屋では、吉田日出子が身寄りのない子供や捨子の世話をしている。彼らばかりで、ひっそりと、したたかに、生きぬいてきたのだ。『盛り場渡り鳥』のおでん屋で、初子(川崎あかね)は、無償の託児所をやっていたが、今度はずっと世話をしようというのだ。国にあずけず、自分たちで。これも「新宿芸能社」につながる“新家族”。実際は、しんどいことだろうに、楽しそうにやっている。そのバイタリズムがいい。叩くと直るテレビは、『喜劇・男は愛矯』でけとばして点灯したダンプのヘッドライトを連想させる。
CMタレント、ヒロミ(栗田ひろみ)にそっくりな女の子を駅で目撃したことから、兄貴の首をつなぐため、チョロ松の旅が始まるのだが、本来の目的であるポン引きは次第に忘れられていくのである。
笠智衆に拾われたヒロミにそっくりな記憶喪失少女・花子(栗田ひろみ)、大船のコイン・ロッカーから拾った赤ん坊、駆け落ちした女子プロレスラーに捨てられた少女(『盛り場渡り鳥』の少女だ)。これら五人組が、森崎さんの“新家族”だ。
モーテル「貴公子」で美女論、強姦論を展開し、名古屋では女子プロレスのレフェリーを務める堺正章の大熱演を、映画は掛値なしに、そのまま見せてくれる。その「動き」は、『幕末太陽伝』のフランキー堺、『渡り鳥』シリーズの小林旭、『にっぽん無責任時代』の植木等のような、自分から動くときの身のこなしの軽やかさとは違うし、キートンの疾走とも違っている。強い者に投げとばされる「被害者的」なものだが、ふだん堺正章が出演しているテレビの小さな画面からは想像もつかない、圧倒的な熱演である。その「被害者的」動きがエスカレートしたあげくに、栗田ひろみが石油缶で女子プロレスラーの頭をガツーンと一撃する。彼女の加勢に、我々は「やった!」と歓声をあげる。そんな喧騒にひきつづいては、静かな看病のシーンである。『喜劇・女売り出します』の岡本茉莉と植田峻か、夏純子と山谷のおカマか。岡本と植田は結びつき、おカマは死んで「浅草様」になってしまうが、さて、この二人はどうなるのか。
 四日市の場面では、『喜劇・生まれかわった為五郎』でハナ肇、緑魔子、財津一郎がやけにちっぽけに見えた、あの巨大なコンビナートが見える。 四日市の場面では、『喜劇・生まれかわった為五郎』でハナ肇、緑魔子、財津一郎がやけにちっぽけに見えた、あの巨大なコンビナートが見える。
彦根・瀬田・岡山・広島・岩国・柳井・壇の浦・関門橋と旅をして、九州へ入る。雨の岩国で、万引のプロフェッショナル・ヒッピーたちの暖かい贈りもの、チョコレートなんかが次々に差し出されるのは、とても楽しいシーンである。善意の人々を描いた昔のアメリカ映画に、きっとこんな暖かいシーンがあったんだと思わされる。そしてまた、心暖まる忘れもの=破れた番傘も登場する。
筑豊、そして有明海は、森崎さんのふるさとでもある。「坑へ下りる男と女は、ほこらの前で手を合わせれば、夫婦になれた」という昔語りがある。生まれたまんまの、飾り気のない、男と女の結びつき。これは、すべての森崎映画にあるテーマだ。『喜劇・女は度胸』での親子どんぶり論。『男はつらいよ・フーテンの寅』の春川ますみ、香山美子と河原崎健三。『喜劇・男は愛僑』のホテルの外での渥美清と寺尾聡の対話。『女生きてます』シリーズの男たち女たち。
「好きなら好きとはっきりいえんのか」。美女論や強姦論のなかの森崎さんらしさとは、「人と人の結びつきは、うわべではない」ということだ。当然のことである。誰しも虚飾をかなぐり捨てて裸になりたいと思っているのである。「原人間」へのあこがれ。原人間がたやすく取り返せるとは思えない。現実には、原人間なんて、むしろ厄介で生きにくくさえあろう。森崎映画の世界でだけ、成り立つ原像なのかもしれない。しかし、永遠にかなわぬ望みであるとしても、憧れだけは持ちつづけたい。
四十七年ぶりに九州の有明の故郷に帰ってきた笠智衆に、三木のり平は、たまっていた言葉をぶつける。音信のないブラジルへお前が行ったきりの四十七年間、恋敵の子を妊んだ娘と結婚し、その子供を育てて、どんな想いで生きてきたか、と。しかし、一方、笠智衆もブラジルでどんな想いで生きてきたか。彼のカバンからは、出発したときのままの日用品しか出てこなかったではないか。おたがいに単純に「わかって」もらわなくてもよいのだ。ただ怒りをぶつけるか、黙って身をひくか、それ以上のことはどちらにも出来ないのである。
 老人が銀行強盗で得た金を持って、東京へ戻って来たチョロ松と花子を、待っているのは兄である。いまやその気がないチョロ松を尻目に、兄は好色な社長へ花子をあてがおうとする。花子は本物のCMタレント「ヒロミ」だったということがわかるのだが、殺人的スケジュールに心身ともに疲れていたヒロミは、ずっと花子として、毛のポンチョを着てスニーカーをはき、ジーパン姿で素顔を表していたのだった。 老人が銀行強盗で得た金を持って、東京へ戻って来たチョロ松と花子を、待っているのは兄である。いまやその気がないチョロ松を尻目に、兄は好色な社長へ花子をあてがおうとする。花子は本物のCMタレント「ヒロミ」だったということがわかるのだが、殺人的スケジュールに心身ともに疲れていたヒロミは、ずっと花子として、毛のポンチョを着てスニーカーをはき、ジーパン姿で素顔を表していたのだった。
マネージャーに連れ去られる瞬間、留置所のチョロ松をふりかえるヒロミは、あるいは港へ車でかけつけようとして事故にあったというヒロミは、『喜劇・女生きてます』で、道路に飛び出し、手をふったポチ(久万里由香)を思わせる。事故で本物のヒロミが死んだ後でも、テレビでは「みんな、元気で生きていこうねーっ」と、ヒロミが出ている豊国生命のCMをやっているという悲しさ。
結末はハッピー・エンドにならずに、「どっか変だぞ」という欄干の上の踊り(=叫びといってもいいだろう)とともに終わる。しかし、この叫びも、見ている子供たちによって対照化されていることを忘れまい。
また、ラスト近くで描かれている、財津一郎と吉田日出子の結びつきは、一種のハッピー・エンド=ハッピー・スタートなのだ。
(個人誌「幻の天使」未刊より)
森崎東監督『喜劇・特出しヒモ天国』(1975年)について 池田博明
今年も森崎さんの映画が見られた。東映初演出の『喜劇・特出しヒモ天国』。
予告編のうたい文句では、東映の新喜劇路線第一弾ということであった。けれど、興行的にパッとしなかったので、後続は出ないらしい。当れば東映で続いてメガホンを取る森崎東という事態になったかもしれないが。世間の風は冷たいなあ。
 林征二が『話の特集』に連載した『ヒモ』が原作。大和書房から単行本が出ている。映画化以前に「ヤングコミック」誌上で、神田たけ志により劇画化されている。 林征二が『話の特集』に連載した『ヒモ』が原作。大和書房から単行本が出ている。映画化以前に「ヤングコミック」誌上で、神田たけ志により劇画化されている。
さて、映画。
エピソード集といっていい。フェイド・アウトでエピソードをつないでゆく。新宿芸能社を中心とする「女生きてます」シリーズでも、森崎映画はフェイド・アウトを多用していた。
どのエピソードも印象的なものだった。原作に登場する人物とそのエピソードをいくつか合わせて、映画ではひとりの人物のキャラクターにしている。原作から名前とキャラクターのほんの一部を借りた場合もある。
原作とのつきあわせは、脚本に森崎さんが加わっていないこの映画に、かえって脚本家・森崎東の意図を読み込む意味があろう。
僕が最も鮮烈なショックを受けたのは、巻頭に登場する殿山泰司の説教僧である。その説教の声、リズム、そしてまた説教をじっと聞くおばあさんたちだった。真夏に身動きもせず、説教を聞くおばあさんたち。マイクをつかい、台の上の拡声器から流れ出る説教の内容といえば、
死んだらどこへいくかということを考えてみて
だれにもわかるもんやない
わからんでええ、わからんでもええ
わからんからこそ 幸せや
なあ、おばあちゃん、あんたら、あたしのいうことがわからんやろ
わからんでええのや、わかってしもたらおしまいや
(中略.バックのイキのいい音楽と説教の文句が他のシーンにかぶさるため、何と言っているのかよくわからない)
なんのことかわからんでもええ
ありがたいお説教を聞いておると、自然に頭が下がってくるやろ、おばあ
これが人間や!生きるっちゅうことや!
死ぬるっちゅうことや!
これさえわかっとったら極楽成就まちがいなしや!
(おばあさんたち、念仏らしきものを唱えながら頭を下げる)
わかったらそれでええ
早う死ぬるこっちゃ 早い方が身の為じゃぞえ
タイトルバックにこの説教が流れたときにはもう唖然、なにがなにやら分からないけれど、ともかく「わからんでもええ」と「死ぬ」という言葉が耳に残った。瞼の裏にはおばあさんたちの姿がはりついて離れなくなってしまったのだ。
この説教僧は原作にはない。あとの説教に出てくる「生者必滅、会者定離」の確認が、僕に感じさせた一番のことは、だから生を大切にしたいということではなかった。
人間の生は限りあるものであり、生が終われば、あとはただ無なのだ。過去も現在も未来もない。ただの無。そのことを受け入れようではないか。
まったく意味のない世界。無時間世界。無感覚世界。
意味のしがらみを抜けた自由な世界。説教の彼方に、僕はそんな無の、自由な世界を感じた。英語ではfreeとは無であり自由なのだ。
死の世界が無の世界というのではない。そう言ってしまえば生の世界が有となり、ただ生に対して死が対置されるだけだ。
全き無。無それ自体。
山城新伍が刺されて洗剤にまみれてころがるシーンに殿山の声で説教が流れる。
人間はみな死ぬんじゃ
おまえらはみな死ぬるんじゃ (略)
どんなことがあっても助かる望みはない
ええか、ここが肝心のところじゃぞえ (略)
たすかろうと思うのが間違いじゃ
生きてる間はたすからん!
あの世に行ってもたすからん!
未来永劫、たすかりゃせんのじゃ!
南無阿弥陀仏
この世にも、あの世にも「救い」という意味はないのだ。この思想は大きい。考えてみれば、宗教はすべて意味の体系なのだ。
この説教が表現しているのは積極的ニヒリズムである。唯一の原則は人間が生まれること、そして人間が死ぬこと。他にニヒリズムの意味はない。
老人には時間がない。一分一秒を問題にするような感覚がない。老人の時間は飛躍的である。老人は突然幼時の体験を思い出したり、次の瞬間にはもう忘れてしまっている。
老人に比べると青年は意味づけの世界に生きている。無意味な行為にさえ、意味がある。しかし、意味のうえに意味を重ねていって、いきついた先はいったいどうなるのだろうか。
善さん一家の葬式が行われている小屋。夏、外からじっと立って見ている子供たちがワン・カット描かれる。森崎映画に点景として描かれる子供には重要な意味がある。森崎さんのテレビ・ドラマ『わが楽園』は、父子寮の子供たちが、父を見捨てて自分たちだけで北海道へ行くために、上野駅構内をぞろぞろ歩いて行く後ろ姿で終わっていた。
子供は大人予備隊ではない。子供自体なにものかである、ということだろうか。
他に原作にないのは、チューリップ・ローズ(芹明香)と元刑事のヒモ(川谷拓三)のエピソードである。アル中のストリッパー・洋子ちゃんのことは、「やどかり善さん」の章にあった。
かほる(森崎由紀)が立ち往生した後で力強く踊り出す感激的エピソードは映画のオリジナル。ただし、おしの夫婦のことは原作にある。
狂言回し風ながら、やっぱり主役の山城新伍と池玲子のエピソードは、ほとんどが映画のオリジナルであった。
山城新伍が川谷拓三に刺されるシーンはみごとなスローモーションだが、このエピソードも映画のオリジナル。
屋台の客で渡瀬恒彦と深作欣二出演。手入れのシーンに汐路章出演。
(『幻の天使』24号.1975年9月21日発行)
「私をつかまえてくれ」と訴える人間ふたり。
府警の一斉手入れをくらったA級京都。そこで家事をするバアさんがいた。刑事を殴ったりして大奮闘。なんとなく申し訳なさそうなのがいい。しかし、彼女は連行されないのである。
「なんでわたしをつれていかへんのや」とくってかかるバアさんに、刑事は殴られた額をおさえながら、「オバちゃんはええ」と答える。「わてかて昔は裸になってたんやで!」とバアさんは叫ぶ。
一方、山城新伍を刺した川谷拓三は地面をたたいて訴える。
「なんで、なんで、オラをつかまえんが。オラァ、オラァ、人殺しぞよ!」
なぜ人間として遇しないのだ。もとヒモの酔いどれがヒモを刺した。殺す方も殺される方もヒモである。とるにたらぬ人間。人間失格のヒモ。そんな風に考えがちである。
ヒモだって人間である。
判断力の低い人間は罰せられない。未成年者や精神に障害のある者。罰するに値しないというわけである。
もと特出しのバアさんは、わたしも罰するに値するのだと主張する。人間としての誇りがある。
「私を罰してくれ」という人物の設定が罰する者の偏見と理不尽な性格をきわだたせる。
『喜劇・女は男のふるさとヨ』で、中村メイコは緑魔子のことで警察にくってかかっていた。高校生の自殺を止めた、止めるのに他の方法を知らなかった、なのにそれがどうして猥褻物陳列なのか。「どうして罪になるんですか?!」と。
刑事・山本麟一(彼は『喜劇・男は愛嬌』でも刑事役)が「おかみ!売春のあっせんをしてるくらい、わかってるんだ」、シッポをきっとつかまえてやるというに及んで、中村メイコの怒りは頂点に達する。先入観と連想で、人間をきめつけることに対する怒り。
『喜劇・女売り出します』では、市原悦子がスリときめつめられたことに対してハラを立てる。ホンモノのスリの方が身なりがよくって上品そうだったからって、と怒る。
森崎さんが脚本を書いた『今日夢人間』(1973年10月13日.NHKテレビ)では、山本陽子が警察にくってかかっていた。花紀京と「籍にも入っていないし、長い間別れて暮らしてるからって、エ、何ですか。最近は、警察は夫婦がねるのにもいちいち許可がいるんですか」と。
これらと同系の人物が『特出しヒモ天国』の芹明香。連行されながら叫ぶ。「あるもん見せて、どこが悪いんや、このドアホ!」「うちは見せたる!」と。
女たちが堂々と生きていくのに対し、男たちは哀れである。山城新伍は血がだいぶ流れてしまって、「寒いなあ」と繰り返す。「寒いのんが、おいどの方からジワジワあがってきよるんや」と。
そして、ローズが自分のもとに帰ってきてくれるかどうかを心配している。病院の払いもあるし、「帰ってきてくれなんだら、さっぱりワヤや」と弱々しい。
『街の灯』で、いくら「愛情仕掛人」と自称してみても、結局はただのポン引きにすぎない堺正章の無力さが心を衝いた。そしてまた、堺正章は自分の無力さを自覚し、やりきれないでいるのが、心を衝いた。堺正章はラストシーンでは橋の上で「ドッカ変ダゾ」と繰り返し言っていた。
人間であることに変わりはないといくら言ってみても、「ヒモ」はやはり哀れな存在なのだ。ヒモ人生を立派に持ちあげることなどを、森崎さんはしていないし、原作者の林征二もしていない。『喜劇・女は男のふるさとヨ』で、頭の弱いアオカン星子(緑魔子)はケチで助平な爺さん(伴淳三郎)に嫁ぐことになったのだった。『喜劇・女生きてます』で、またたび笠子(倍賞美津子)は結婚し、ポチ(久万里由香)は足の悪いおにいちゃんに嫁ぐ。『喜劇・女売り出します』で米倉斉加年は八丈島で百姓をする。
そして『特出しヒモ天国』でター坊(下条アトム)とかほる(森崎由紀)の聾唖の夫婦はストリップで出産資金をかせぎ、丈夫な子供を産むのである。
『喜劇・女は度胸』にこんなセリフがあった。「家庭とはホームなんだ。ホームとは生活の場なんだ」。だからこそ、ホステス(久里千春)も亭主と子供の待っている家庭へ帰るのだった。フーテンの寅さんなら、「さすがインテリ、うまいこというじゃねえか」と言うところだ。
森崎東色の濃い初期の『男はつらいよ』が「フーテン」の寅と「かたぎ」のオイちゃんたちの衝突で成り立っていたように、いまでも森崎さんはふたつの間の緊張関係をドラマのひとつの軸にしている。寅の舎弟分の津坂匡章の姿が消えてしまってからというもの、『男はつらいよ』における「フーテン」の力は減衰したと思われる。「兄貴ーっ!」という弟分のフーテンへの憧れのまなざしが、形を無くした頃から、『男はつらいよ』が自分にとっては遠くなった。
マジメで、言うことがいちいちもっともな寅さんには、あまり魅力がない。よく考えてみると、いつも、もっともなことを言う寅さんだったけれども、それを「馬鹿だねェ」と笑う人たちがいなくなって、みんながみんな優しくなってしまった。周囲のみんなが「さくら」と同じになってしまったのだ。「わかるわ、おにいちゃんの気持ち。そうよネ」というのは、さくらだけでいいのだ。
『特出しヒモ天国』で踊りの途中でテープが故障し、立ち往生してしまう森崎由紀。彼女は客たちを見下ろす。そこで初めて彼女は客の「視線」に出会う。多くのまなざしに彼女は耐える。
もし、テープの故障がなければ、耳が聞こえない彼女は自分の内面の世界だけの「バラが咲いた」に合わせて踊っていればよかった。客が聞く「バラが咲いた」と表面上は一致していても、実際は客とはなんの接点もない。ところが、である。
舞台の上で客のまなざしに耐える彼女。カメラは舞台の後方へ回り、立っている彼女の後ろ姿と、彼女をはやす客をとらえる。照明がまぶしい。音は消してある。画面はいま彼女の世界になっている。
そして、キッと、彼女は足を高くあげ、堂々と踊り出す。客のまなざしをはね返して、まなざしに応えて、彼女は客と関わる。自分を確立する。
みごとだ。美しい。客は大喝采する。
映画館でも拍手が起こってもおかしくないところだ。
僕も涙が出た。赤ん坊誕生のシーンでもまた涙・・・。
ある批評家が『特出しヒモ天国』につけた注文が「笑いの再検討」だが、そんなものは森崎喜劇に必要ではない。森崎映画を「笑えない」などと批判するのは間違っている。喜劇というレッテルと批評者自身の喜劇観で作品を見る前に映画を規定してしまうのは奇妙である。
僕には、4年前に初めて森崎喜劇を見たとき、「これは喜劇ではない」とか「喜劇なのに笑えない」という感想はなかった。そんなことはどうでもよかった。ただ、心に残った。そして、混乱した。うまく説明できなかった。
そして、その混乱に言葉を与えようと、森崎さんの映画を見てみようと、心に決めた。いまこのスタート地点のことを大切にしようと思っている。 (『幻の天使』25号.1975年9月25日発行.一部修正)
喜劇 特出しヒモ天国(東映 森崎東監督) 池田博明
不遇の傑作『街の灯』から、森崎さんの語り口はいよいよ冴えてくる。きどらずきばらずけれんなく、淡々とおとことおんなの生命の詩を描き出す。おとこがいて、おんながいる。そこに噺がある。
「京都の町がのうなっても、ストリップはのうならんで!」
時代がいかに変わろうとも、ひとのいのちのいとおしさは変わらない。
生者必滅、会者定離。だれでも年を取る。年を取ればトクダシさんもヒモもツトメが大変になる。そしてだれもいつかは死ぬ。しかし、死ぬからこそ生命が尊いのである。別れるから出会いを大切にしたいのである。あたりまえのことが清新に思える。ろうあ者の夫婦が懸命に踊り、子供を産むエピソードに心打たれない人は、よほど不幸な人であろう。
親子四人が焼け死んでも、人がひとり殺されても、殺しても、天下泰平である。広大な宇宙の前では人間はまったくつまらない存在であるという科学の主張は正しいのだろう。しかし、だとすれば、なんとつまらない科学を人間は築いてきたことか。よかれと思って整備してきた法律が、人間性をしばっているように。
TV『わが楽園』(森崎東脚本)で突如アル中になることを決意したおじいさんの論理は、アル中になって酒で税金を払い、国のためになろうというものだ。なるほど!
法律とはそういうものだ。だが、そうあってはならないのだ。
アル中のチューリップ・ローズ(芹明香)が護送車の中から、きっと眼を見開いた表情のアップで映画は終わる。『街の灯』の堺正章の「どっか変だゾ」やTVの中の栗田ひろみの「みんな、元気で生きていこうねーっ」と照応するラスト・シーンである。説経僧(殿山泰司)が「たすからん」ととなえるたびに、森崎さんの不屈な意志が伝わってくるように、不屈のラスト・シーンである。
(キネマ旬報「読者の映画評」1975年8月上旬号〔663〕)
森崎東監督『ロケーション』(松竹) 池田博明
 超傑作である。この作品はビデオ化されているので、多言を要しないかもしれない。原作はピンク映画を撮影するときの苦労話や裏話なのに、映画の方は母親と娘の奇っ怪なドラマ(脚本は近藤昭二と森崎東)に仕上がってしまった。 超傑作である。この作品はビデオ化されているので、多言を要しないかもしれない。原作はピンク映画を撮影するときの苦労話や裏話なのに、映画の方は母親と娘の奇っ怪なドラマ(脚本は近藤昭二と森崎東)に仕上がってしまった。
ピンク映画のカメラマンであるベーやん(西田敏行)は、女房で、主演女優の奈津子(大楠道代)の自殺未遂で、ほとほと困ってしまう。たまたまロケ現場として借りた連れ込み宿の掃除婦エミ子(美保純)を発見、急きょ主演女優の代役にしたてて、映画を完成させようとする。しかし、少し撮影したところで、監督(加藤武)は倒れるわ、エミ子は自分の田舎に墓参りに帰ると言い出すわ、次々に難関が襲ってくる。
エミ子の帰郷に合わせて、その場その場で脚本を変えながら、撮影するうちに、エミ子の過去が明らかになっていく。ピンク映画の台本と、彼女の人生がないまぜになって、フィルムに記録されていくという物語である。ピンク映画のスタッフ役では、柄本明(脚本家役)・竹中直人(助監督役)・河原さぶなど魅力的な役者が顔をそろえている。
森崎映画の魅力的な小道具は満載されている。
夜明けの街並み、豆腐屋の2階の部屋、ベーやんの愛唱歌「エイトマン」の主題歌、室内にしつらえた風呂。ピンク映画をやめたら、やろうとしている堅気の仕事は「ホカホカ弁当屋」だと言う。
スタッフそろっての一本じめ、湯本温泉郷、石積みの墓地、つげ義春の「ゲンセン館主人」に登場するような紙風船売りのおばあさん、場末の映画館(館主は殿山泰司)、海岸の掘っ立て小屋、幼稚園の園児たち、海草取りのおばあさん、紙風船。美保純が無理矢理着て破ける少女時代のシュミーズとランドセル。ひとりふた役などなど。
また、森崎映画のダイナミズムも素晴らしい。素っ裸で寝ている少女が死体のように現われてくるシーンの見事さ。室内から外の道路へ、小屋から浜や森へ、女優を追って走り出すスタッフたち。母と娘の誤解と和解の物語。
ピンク映画の脚本は、少女が次々に自分をだました男たちを誘惑して殺害し、復讐するというものだった。しかし、エミ子の中学時代の体操教師(佐藤B作)から、意外な事実がスタッフに伝えられる。エミ子には小学生時代から母親殺しの噂があった、母親が父親を殺したからだという。貧乏から心中を図ったあげく、娘ひとりが生き残ってしまったのだという。不幸な少女の物語である。エミ子に水泳の個人指導をした体操教師は、彼女を誘惑した過去があり、映画の撮影を複雑な思いで見つめているが、とうとう自虐の念から「俺を殺せ!」と、プールにとびこんでしまう。
 しかし、そんな過去の不幸物語が、エミ子の故郷で、奈津子にそっくりな娼婦(大楠道代の二役)が登場するあたりから、ねじれてくる。どこまでが幻想で、どこからが現実なのかが、混沌としてくる。(見直してみると、物語上は幻想場面はほとんどなかった。つまりエミ子と母親の物語は過去の事実として描かれていた) しかし、そんな過去の不幸物語が、エミ子の故郷で、奈津子にそっくりな娼婦(大楠道代の二役)が登場するあたりから、ねじれてくる。どこまでが幻想で、どこからが現実なのかが、混沌としてくる。(見直してみると、物語上は幻想場面はほとんどなかった。つまりエミ子と母親の物語は過去の事実として描かれていた)
海辺の掘っ立て小屋で、母親と娘が出会い、過去の真実を再現する。娘には母親が父親を殺したという記憶がある。しかし、実は死を決意した夫婦が今生の別れに夫婦の契りを交わしているのを、海藻取りから帰って来て、少女は目撃したのだという。
娘「嘘だ!なぜ父親だけが死んで、お前だけが金持ちの妾になって生きているんだよ?」
母「嘘じゃねえ。仕方がなかったんだよ。それでもよかったじゃないか。その証拠にお前も俺も生きてっぺ」
娘「生きてなんかいねえ!(親殺しの罪をきて、いままで)俺は死んでたんだよ!」。
唖然としながら、スタッフはこのドラマをカメラにおさめ続ける。
さらに、過去が再現される。娘が家を飛び出し、夫婦は娘を追いかけた。断崖絶壁で、娘は樹にくくられた。そこで母親は、父親を突き落とした。いや、実際は父親が自分から海へ飛びこんだのだ。
娘「なぜ(お前は)後を追わなかったんだ。こわかったんだろ?飛んでみろ」。
母「お前を残して死ねるか。いまなら飛び込めるんだ」と母親は飛び込もうとする。ギリギリのところで、本気の母親に、しがみついて止める娘。二人はなんとか和解した。
いきがかりで関わることになってしまった他人の人生へのこだわり。そんなこだわりが映画のなかの物語を動かす。同じような構造は『街の灯』にも『喜劇・女売り出します』にもあった。
 べーやんは脚本家(柄本明)に、よく「何きどってんだ?自分の国の言葉(方言)でしゃべれ!」と言う。エミ子(美保純)は幼児体験が影響して、無口である。しかし、最後に母親と対決したときには、エミ子は奔ばしるように母親批判の言葉を投げつける。この映画は、自分の言葉(表現力)を失った者たちが、言葉(表現力)を回復する物語でもある。 べーやんは脚本家(柄本明)に、よく「何きどってんだ?自分の国の言葉(方言)でしゃべれ!」と言う。エミ子(美保純)は幼児体験が影響して、無口である。しかし、最後に母親と対決したときには、エミ子は奔ばしるように母親批判の言葉を投げつける。この映画は、自分の言葉(表現力)を失った者たちが、言葉(表現力)を回復する物語でもある。
虚構と現実がないまぜになった作品を、試写で見た監督(加藤武)は「傑作だ。ナっちゃん、うまくなったね。最初と最後じゃ別人だよ」と言う。しかし、配給会社の社員(矢崎滋)は、「こんなわけのわからないものを会社に持って帰ったらクビだ!」と配給を拒否する。上映されない映画に、意味はない。それでも、ベーやんはフィルムを缶ごと持ち帰る。豆腐屋の夫婦(愛川欽也・吉田日出子)が「エイトマン」の歌を歌って激励してくれる。べーやんは室内の風呂にゆっくり体を沈ませる。奈津子が帰ってきて寝ている。
フィルムには人生の一瞬一瞬が記録されている。それだけで映画の価値はある。
おそらく美保純がもっとも美しかったときの最高傑作である。それまでピンク映画に出ていた竹中直人が最初に一般映画に出演した作品でもある。
増田俊光氏の ロケーション撮影裏話のページがある ▼http://home.att.ne.jp/gold/drugstore/masuda/mt024.htm
ページは削除・消失することがあるので
文字データだけ、わがページ内に保存してあります。
森崎東監督『ラブ・レター』(松竹) 池田博明
この作品はビデオ化されている。森崎さんらしい映画であった。
猥雑な人間や背景を点景として取り込む森崎節は健在で、前半はかなりの数の森崎らしさがつめこまれていた。「女」シリーズの新宿芸能社があった新宿ゴールデン街まで出てくるし、中井貴一が歩く後ろに、ホームレスの連中までがちゃんと(エキストラとして)映しこまれている。中井貴一が自室で風呂に入っているのは明らかに『ロケーション』のベーやんを連想させるところだ。原作は浅田次郎の短編小説。
森崎東脚本・監督『黒木太郎の愛と冒険』(ATG) 池田博明
 昭和52年(1977年)公開のATG(アート・シアター・ギルド)映画。公開当時に見た時は、映画のスタントマン・黒木太郎(田中邦衛)が、暴力団の事務所に乗り込む際の画面に感心した記憶がある。構図や緊張感が黒澤明の映画以上だったのだ。 昭和52年(1977年)公開のATG(アート・シアター・ギルド)映画。公開当時に見た時は、映画のスタントマン・黒木太郎(田中邦衛)が、暴力団の事務所に乗り込む際の画面に感心した記憶がある。構図や緊張感が黒澤明の映画以上だったのだ。
映画のなかに、森崎さんの実兄で、終戦直後に割腹自殺した森崎湊の本『遺書』が出て来るので、当時の森崎映画のよき理解者、白井佳夫さんの「この映画は森崎さんのいわば8
1/2だが、失敗作」という評価が念頭から離れずに、見てしまった。ATGで公開した作品の中では、おそらくもっとも不入りで、かつ不評だった映画である。しかも白黒作品。
BS2のミッドナイト映画劇場で、2001年8月21日にATGの『股旅』(市川昆監督)が、そして22日に、この映画が放映されるはずだった。ところが、台風情報のため、一週間延期になったのだった。ようやく満を持して、私にとっては24年後に2回目を見ることができた。
2回目を見て、森崎さんがこの映画にこめた想いがやっと分かったような気がした。森崎さんの兄・湊が『遺書』に書き遺した、戦争を憤り、そして戦後にかけた呪詛の言葉はそのまま、現代に当てはまるのだ。“いまは戦争中”なのだった。
出演しただけで、森崎ワールドをかもし出す役者たち。主役・黒木太郎の田中邦衛。そして、太郎の妻・倍賞美津子、おおばあ・清川虹子、ちいばあ・沖山秀子、ネコ狂いの女教師・緑魔子。これら重量級の女優の存在が圧巻である。
三人の若者は狂言まわしの役どころだが、ガン(伊藤潤)は映画の語り手でもある。
 男たちも森崎映画の常連たちで、「大人のオモチャ」屋の財津一郎、飲んだくれて汚物を片付け横死する伴淳三郎、若者ガンの父でガダルカナル戦で生き残った砲兵隊長・三国連太郎、おおばあに惚れている小沢昭一、酒場の飲み仲間で割腹自殺を目撃してしまう井川比佐志、飲み仲間の火野正平、飲み仲間の殿山泰司。 男たちも森崎映画の常連たちで、「大人のオモチャ」屋の財津一郎、飲んだくれて汚物を片付け横死する伴淳三郎、若者ガンの父でガダルカナル戦で生き残った砲兵隊長・三国連太郎、おおばあに惚れている小沢昭一、酒場の飲み仲間で割腹自殺を目撃してしまう井川比佐志、飲み仲間の火野正平、飲み仲間の殿山泰司。
そして聾唖の貧乏夫婦の妻役を、当時東映のスケバン女優だった杉本美樹がノミにくいつかれた感じで汚く(!)演じている!夫役は岡本喜八監督である。
一枚の画面に映し出されるヒトや風景は、過剰なメッセージを持っていて、それを受け取る観客の精神こそが、映画の意味を作り出す。単調な精神で見れば、映画はひどく散漫なつまらない物語に見えてしまう。森崎映画の過剰なメッセージは、物語を内部から破壊してしまう。
ちなみに、この映画でもっとも可笑しいのは財津一郎である。彼の芸は特別製である。この映画で彼の口癖は「ニワトリはハダシよ」。いったいこの言葉の意味はなんだろう?
彼の説明によると、「お手上げだ」ということだそうだが。なぜそんな意味になるのか、繰り返されるうちになんとなく納得できてしまうから、不思議だ。《「ニワトリはハダシだ」の意味は、当たり前のことを当たり前とすることでした》
いまどきだったら、こんなに非商業的な映画は作れません。
『ニワトリはハダシだ』 池田博明
『ニワトリはハダシだ』 製作総指揮・志摩敏樹、製作・若杉正明、脚本・近藤昭二・森崎東、出演・肘井美佳、石橋蓮司、加瀬亮、余貴美子、岸辺一徳、柄本明、笑福亭松之助、塩見三省、李麗仙、倍賞美津子、原田芳雄。監督・森崎東
森崎東監督の新作が公開準備中である。題名は『ニワトリはハダシだ』。スタッフは脚本は近藤昭二・森崎東、撮影・浜田毅、キャストは倍賞美津子・原田芳雄・柄本明という森崎組に、李麗仙・岸辺一徳という曲者揃いである。そこへ新人が入り込む。
『映画芸術』54巻1号(2004年)で加瀬亮と森崎東にインタビューしていた。
新人の一人、加瀬亮は主演の映画『アンテナ』(熊切和嘉監督)と全く異なった森崎組にかなり戸惑ったらしい。しかし、最後になってようやく違う世界の映画作りが理解できたという。「最初、森崎監督がこれは喜劇だとおっしゃっているのが、僕には全然わからなかったんです。・・・面白くない人間なんていない、面白いひとがいるのではなくて、人間そのものが面白いのだと。・・・森崎組に参加してみて一番感じたことは、映画は理屈じゃないんだということ。そこにいることが映画として面白ければそれでいいんだということ。」
加瀬君の把握は森崎映画の根幹を衝いていると思えた。『ロケーション』の魅力もそこにあった。脚本家の荒井晴彦が『さよならクロ』にふれて、「いま若手で撮影所育ちのようにルーチンをこなせるのは松岡錠司しかいない」と書いているが、『バタアシ金魚』の松岡錠司に「森崎節」を感じた私としては、スクリーンに面白い人間が映し出されていることが映画の力だと思うのである。CG合成や特殊撮影で物語はちょっとだけというのが最近の映画だが、それでは映画の活力は出て来ない。
「ニワトリはハダシだ」とは一体何を意味しているのだろうか。『黒木太郎の愛と冒険』(1972年ATG)で財津一郎が言う台詞である。
森崎さんはこんな風に言っている。「世の中が普通ではない、普遍的ではないように動いている、まるでニワトリが靴を履いていることになっているんじゃないか」と。よく見れば「ニワトリはハダシじゃないか」。当たり前のことを当たり前に見ろと言っているのである。
森崎さんによると「最初に考えていたタイトルは『五十六億七千万年前の遅刻』というものでした。・・・弥勒菩薩が現れて人を救うのは釈迦の入滅後、五十六億七千万年たってから。そんなに待ってはいられないという」主人公の若者・直子の台詞から。
しかし、製作者・志摩氏が「そういう理屈っぽい題名よりも、ズバッと放り出したようなものがいいです」と言うので、提案した題名だった。
俳優さんに「間をつめてくれ」と言ってましたが(インタビューアーの榎戸耕史)と問われて、
森崎「間を置くことが芝居だと役者は思っていますよね。しかし、間を作られるということは、僕ら演出側からすればそれだけ芝居が少なくなるということじゃないですか。・・・・
清水宏監督作品では『港の日本娘』(1933年)は嫌いなんです。それは単純に上流階級の話だから。」
|

 ◆11月16日は渋谷ユーロスペースでの『ペコロスの母に会いに行く』第1回上映の後、森崎監督・出演者・原作者の舞台挨拶がありました。
◆11月16日は渋谷ユーロスペースでの『ペコロスの母に会いに行く』第1回上映の後、森崎監督・出演者・原作者の舞台挨拶がありました。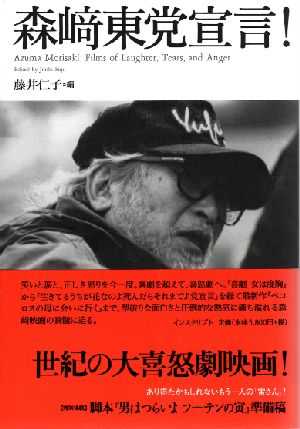

 四日市の場面では、『喜劇・生まれかわった為五郎』でハナ肇、緑魔子、財津一郎がやけにちっぽけに見えた、あの巨大なコンビナートが見える。
四日市の場面では、『喜劇・生まれかわった為五郎』でハナ肇、緑魔子、財津一郎がやけにちっぽけに見えた、あの巨大なコンビナートが見える。 老人が銀行強盗で得た金を持って、東京へ戻って来たチョロ松と花子を、待っているのは兄である。いまやその気がないチョロ松を尻目に、兄は好色な社長へ花子をあてがおうとする。花子は本物のCMタレント「ヒロミ」だったということがわかるのだが、殺人的スケジュールに心身ともに疲れていたヒロミは、ずっと花子として、毛のポンチョを着てスニーカーをはき、ジーパン姿で素顔を表していたのだった。
老人が銀行強盗で得た金を持って、東京へ戻って来たチョロ松と花子を、待っているのは兄である。いまやその気がないチョロ松を尻目に、兄は好色な社長へ花子をあてがおうとする。花子は本物のCMタレント「ヒロミ」だったということがわかるのだが、殺人的スケジュールに心身ともに疲れていたヒロミは、ずっと花子として、毛のポンチョを着てスニーカーをはき、ジーパン姿で素顔を表していたのだった。
 超傑作である。この作品はビデオ化されているので、多言を要しないかもしれない。原作はピンク映画を撮影するときの苦労話や裏話なのに、映画の方は母親と娘の奇っ怪なドラマ(脚本は近藤昭二と森崎東)に仕上がってしまった。
超傑作である。この作品はビデオ化されているので、多言を要しないかもしれない。原作はピンク映画を撮影するときの苦労話や裏話なのに、映画の方は母親と娘の奇っ怪なドラマ(脚本は近藤昭二と森崎東)に仕上がってしまった。
 しかし、そんな過去の不幸物語が、エミ子の故郷で、奈津子にそっくりな娼婦(大楠道代の二役)が登場するあたりから、ねじれてくる。どこまでが幻想で、どこからが現実なのかが、混沌としてくる。(見直してみると、物語上は幻想場面はほとんどなかった。つまりエミ子と母親の物語は過去の事実として描かれていた)
しかし、そんな過去の不幸物語が、エミ子の故郷で、奈津子にそっくりな娼婦(大楠道代の二役)が登場するあたりから、ねじれてくる。どこまでが幻想で、どこからが現実なのかが、混沌としてくる。(見直してみると、物語上は幻想場面はほとんどなかった。つまりエミ子と母親の物語は過去の事実として描かれていた)